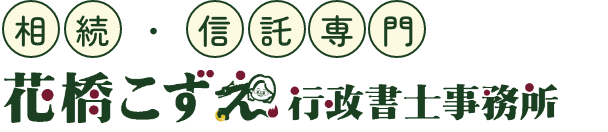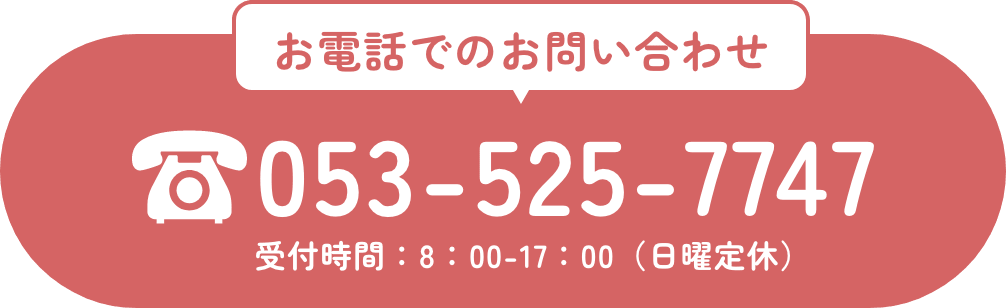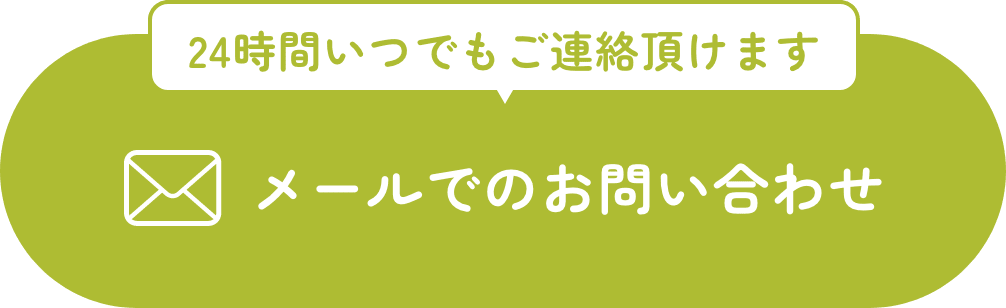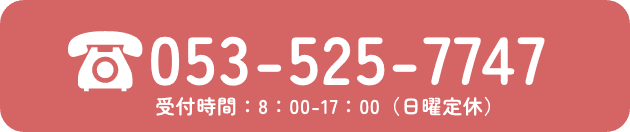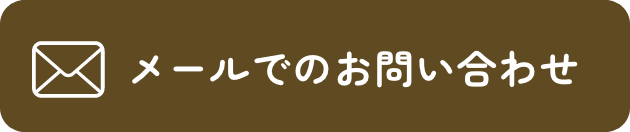相続の単純承認・相続放棄・限定承認とは

民法の915条には、相続の承認又は法規をすべき期間が定められています。条文は以下のとおりです。
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
このように、相続人となった人は3カ月以内に遺産を相続するのか、遺産を限定して相続するのか、又は放棄するのかを決めなければならないんですね。
今日はこの単純承認・限定承認・相続放棄についてお話したいと思います。
3箇月以内に、限定承認または相続放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。
単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。(民法920条)
そして、次の場合にも単純承認したものとみなされます。(下記は条文のとおりです)
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
こちらの条文を簡単に解釈すると、一は、相続財産の一部でも処分してしまったとき、二は、3箇月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき、三は、限定承認や相続放棄をした後でも、相続財産の隠匿等があったときは、相続人は単純承認をしたものとみなされます、ということです。
三の但し書きについて簡単に解釈すると、
次の順位の相続人が相続を承認した後に相続財産の隠匿等があった場合には、単純承認とは扱われないということになります。これは、次順位の相続人の相続についての意思を尊重するということからこのようになっているんですね。
では、限定承認とはどういうことでしょうか?
単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継することになりました。では、限定承認をするとどうなるのでしょう?
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることをいいます。(民法922条)
条文は以下のとおりです。
第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
これをわかりやすく言いますと、相続したプラスの財産を使って負債を返済して、それでも余剰がある場合にのみその財産を相続するということです。
この方法は、相続人の全員が共同して限定承認をしなければなりません。また、3箇月以内に家庭裁判所で限定承認の手続きを行う必要があります。
こちらの限定承認ですが、実際は使われている方はごく少数です。
なぜかというと、3箇月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述をしなければならないなど手続きが煩雑であり、連帯保証人の地位も相続しなければならなかったり、プラスの財産が残っても債権者の権利がすべて消えるわけではないので、なかなか大変です。
もちろん、債権者に公告を行った後に名乗り出てきた債権者に弁済して、プラスの財産が無くなればその後の弁済義務はなくなりますが、この公告期間の後から新たな債権者が名乗り出てきた場合の債権者の権利がなくなるわけではないので、債権の消滅時効が完成するまでは安全とは言えない状況です。
限定承認よりも選ばれやすい相続放棄
この点、相続放棄を選択すれば、遺産の相続を完全に放棄する方法ですので最初から相続人でなかったものとみなされます。以下は条文です。
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
当然、債権者の権利が残ることもありませんから、相続財産に負債が多い場合は大変有効な方法ですね。
また、相続放棄は一人でもできますが、「最初から相続人でなかったものとみなされる」ので、次順位の相続人に相続の権利が移動しますから、もし、負債が多いとの理由で相続放棄を選択する際は、次順位の相続人も相続放棄を選択する方が良いですね。親族間の中でしっかりコミュニケーションをとって、相続放棄をする場合は、みんなで相続放棄をすることが大切です。
いかがですか?マイナスの財産の方が明らかに多い場合は限定承認よりも相続放棄を選んだ方がより安全です。
では、限定承認を選んだ方が良い場合はあるの?
債務が多いのはわかってはいるが、プラスの財産も多いのが確実なケースです。
相続の開始を知ったときからの熟慮期間が3箇月ととても短いですので、相続人の数や負債の額がはっきりとはわからない場合に、プラスの財産も確実に多いとなれば、限定承認という選択もあります。
ですが、そうは言ってもなかなか3箇月以内に決断するのは難しいですよね。
そのようなときは「熟慮期間の伸長の申立て」を家庭裁判所に行うのが良いと思います。ですが、この「熟慮期間の伸長の申立て」も相続の開始を知ったときから3箇月以内に行わなければならないので、ご注意ください。
いかがでしたか?
被相続人が亡くなってから、悲しみの中、ご遺族はこのような相続に関する選択をしなければなりません。本当にあっという間に3箇月はすぎてしまいます。
相続の方法に関する選択だけでなく、お葬式も行わなければならないし、相続手続きも待ってはくれませんから、人が亡くなると本当に大変です。
花橋こずえ行政書士事務所ではこのようなご相談も承っております。初回60分の無料相談をご活用いただければ幸いです。