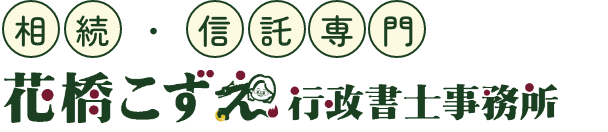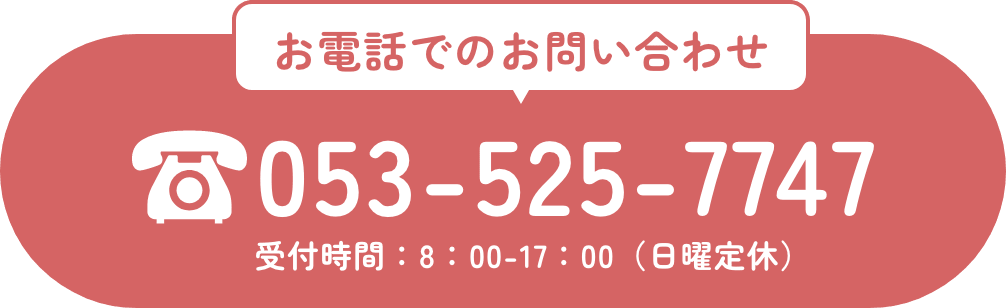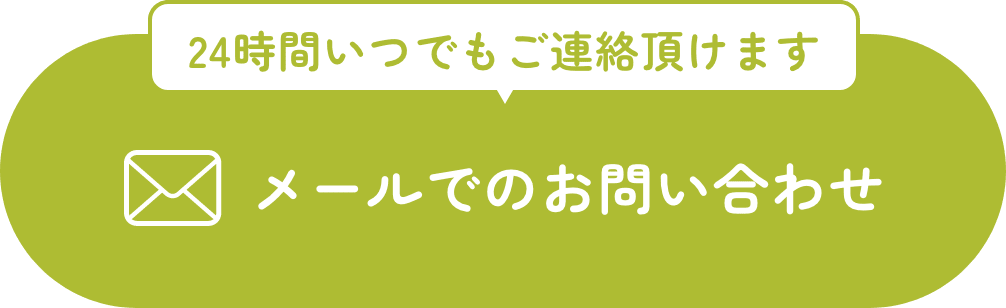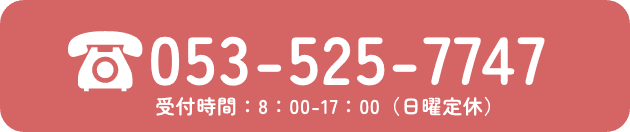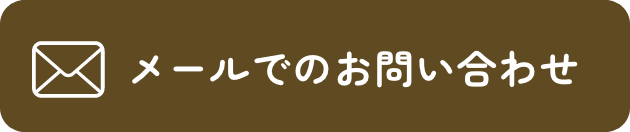家族信託契約書 実際のこんな例②

前回に続いて、家族信託契約書の本当にあった事例②としてお話していきたいと思います。
実は、契約書を作る組織、金融機関、士業によって内容は随分違うものになるんです、というお話を前回させていただきました。
実際に、制約の多い契約書になったり、自由度の高い契約書になったりします。そこで今回も実際にあったお客様からのご要望に対して、私たちチーム(社)民事信託相談センターがどのように対応させていただいたのかをお話したいと思います。
信託監督人を置かなければならないの?
いいえ。そんなことありません。
置いてもいいし、置かなくても良いです。任意なんですね。
ところが、お客様が相談された金融機関では「信託監督人を置かなければならない」と説明を受けたそうです。信託法上は置かなければならない義務は無いのですが、なぜ、その契約書は「信託監督人を置く」ことを義務化しているのでしょうか?
家族信託の良いところは、他人の関与を受けることなく、家族内で財産の管理ができるところです。信託監督人を置くことによって誰かから監督を受けるようになってしまうことは、ご家族が本当に望んでいることでしょうか?
私たちのチーム(民事信託相談センター)は、できるだけ他人の関与を必要とせず、家族内で解決できるような契約書の内容にしておりますので、もちろん、「信託監督人を置くことは、ほぼありません。」
中には、非常に稀ですが、特殊な事情によりご家族のお一人に監督人になっていただいたこともありますが、それもご家族であり、他人の関与を設定していません。
家族信託契約は、法定後見の制度を利用しなくても良いように、事前に対策できる財産管理の方法として大変優れた制度ですので、せっかくの良いところをつぶしてしまわないように、と私たちは考えています。
親が認知症になった後の財産管理では、成年後見制度のお話をよく聞いたことがあると思いますが、成年後見制度(法定後見)では、後見人として選任されるのは実に約8割が弁護士、司法書士などの専門家の方々です。
もちろん、すばらしい人格者であられる先生もおりますが、中には横領して新聞沙汰になってしまう先生もいますね。それに、後見人報酬として毎月2万円~5万円(※ご本人の財産額によって変わります)
を死ぬまでお支払い続けないといけない。これは、大変重荷です。
では、なぜ信託監督人を置くことが必須になっている契約書が存在するのでしょう?
それはおそらく、受託者である財産管理を任された人が、勝手にお金を使ったり、裏切ったり、受託者としての仕事をしないことを想定しているのでしょう。
でも、ここで良く考えてほしいんです。
信託契約は信頼関係を基にする契約です。信頼できない、裏切るかもしれないと思っている方とは、そもそも契約自体するべきではありません。
「自分の信頼する人に自分の財産を託して、管理運用してもらう」ということが大前提ですから、その信頼する人に対して、裏切るかもしれないと、監督人をつけたり、契約の内容が受託者を規制するものであることは本末転倒だと、私たちは考えます。
さて、皆さんはどう思われましたか?
今日は、「信託監督人」についてお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
このように、家族信託契約書は、信託監督人一つとっても、作る人で内容が全然違うものになるんです。
家族信託を運用される皆さん自身が使い勝手がよく、負担の少ない契約書になることを心から願っております。
花橋こずえ行政書士事務所は、相続・信託を専門としています。初回60分間の無料相談時間も設けておりますので、お気軽にご連絡いただければ幸いです。