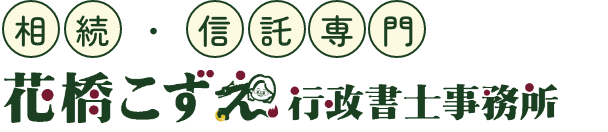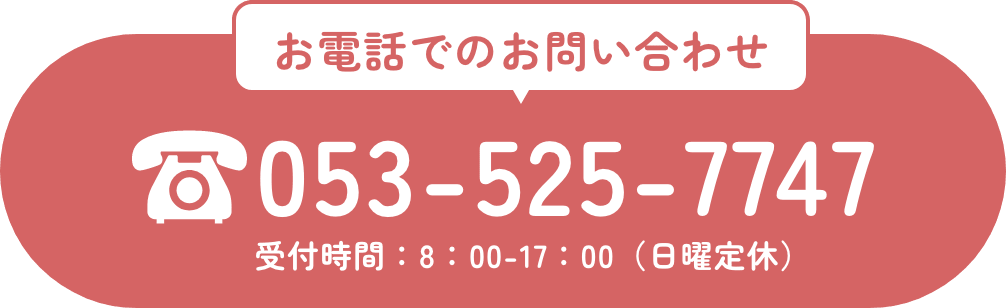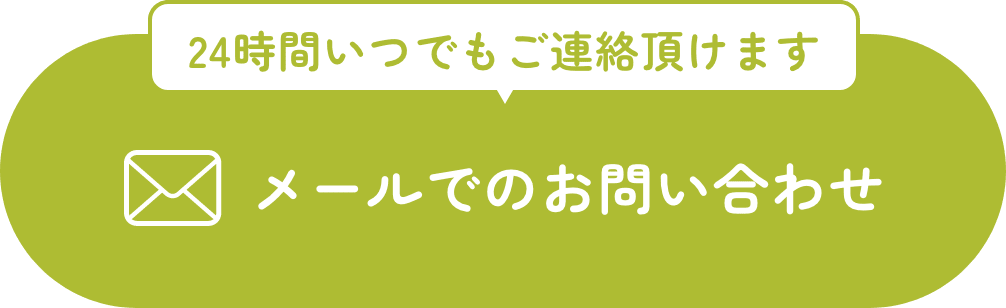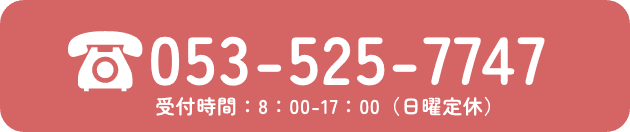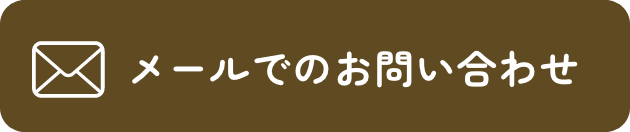実家じまい 早めにしないと大変です!

「そろそろ実家をどうしようか考えないと」と、思われている方、たくさんいらっしゃると思います。田舎の親が高齢になってきて、自分は違う場所に住んでいる。もうその実家を使う予定はない。と思われている方は「実家じまい」を考えられていると思いますが、どうか早めにご決断くださいませ。
なぜなら、親が認知症になってしまったら、実家に手を出せなくなってしまいます。売ることも、貸すことも何もできない。ましてや固定資産税は毎年かかり、管理責任は続きますから、草むしりや立ち木が隣家にかかってしまっていては、枝の切り取りなども管理責任として行わなければなりません。ブロック塀が古くなってきたら、補修も考えないといけません。
万が一、ブロック塀が壊れた際に通行人が怪我をしてしまったら、その責任は原則所有者にかかってきてしまいます。
今日はなぜ、実家じまいは早めに行わないといけないのか、このまま放置したらどうなるのか、などのお話をさせていただきたいと思います。
親はいつまでも元気ではないです。
できる限り元気であってほしいものですが、なかなかそうもいきません。
厚生労働省の発表によると、2022年時点で高齢者のうち認知症と診断されている方は443万人となっており、これは65歳以上の高齢者の12.3%です。 しかし、2025年には認知症患者数が700万人を超え、高齢者の5人に1人が認知症になると予測されているんです。
では、親が認知症になってしまうと、どんな困ることがあるでしょう?
まず、家を売る契約も名義を変える手続きも一切できなくなります。もちろん、貸すこともできません。
まさに手が付けられなくなってしまうんですね。実家じまいはこの瞬間から完全に止まります。
これを回避できる制度として、「法定後見制度」がありますが、皆さんご存じのとおり、法定後見にはデメリットも多数あります。例えば、
①家族が後見人になれるとは限りません。専門家が後見人に選任されれば、死ぬまで報酬を払い続けなければならないです。
②家を売るには、家庭裁判所の許可が必要です。
③他人の関与を受けます。(裁判所や後見人のことです)
④後見人の判断に縛られます。(売る金額も売るタイミングも自分で決められません。)
このようなデメリットがあります。では、任意後見制度はどうか?というと、
任意後見は自分で後見人を選ぶことができる制度ですから、基本的には任意後見人に任せることができるのですが、任意後見契約を締結したからといって、家を売ったり、名義変更したりがすぐできるわけではないのです。
皆さん、任意後見契約を締結したから大丈夫と思われている方がたくさんいらっしゃいますが、実は任意後見制度は、「後見監督人を選任してから」効力が発生するものなんですね。
任意後見を始めるためには、家庭裁判所に後見監督人選任申し立てをしないといけません。この後見監督人は、司法書士や弁護士の先生が付きますので、専門家の先生がお仕事としてやっておられるので、当然、報酬も発生します。法定後見よりは安くはなりますが、毎月、報酬をお支払いすることに変わりはありません。
今のうちに家族信託を検討してみて!
まだ、今、親御さんが元気で、普通に会話ができる状態でしたら家族信託契約を結ぶことができます。
ご実家を信託して、子どもさんに任せることで、他人の関与を受けることなく、継続的な報酬も基本的には発生することなく、子どもさんの好きなときに、好きな方へ売る、名義変更する、貸す、という行為が自由にできるのです。
「他人の関与を受けなくて良い」ことは、大変魅力的なのではないでしょうか。
また、固定資産税もあらかじめ、親御さんがいくらかを子どもさんに託しておくことで、そのお金から支払うことができますから、子どもさんが立て替えることをしなくても良いんです!
ただ、家族信託も、親御さんが元気なうちしかできないことなんですね。
認知症になってしまったら、家族信託もできなくなってしまう。実家じまいもできなくなってしまう。銀行からお金をおろすこともできなくなってしまう。固定資産税は毎年払い続けないといけない。
本当に大変なことがたくさんあって、周りのご家族が苦労されますので、ぜひ、今のうちに、家族信託をご検討いただければ幸いです。
花橋こずえ行政書士事務所では、定期的に家族信託セミナーも開催しております。ZOOMを使ったオンラインも湖西市の不動産やさんでの対面もどちらもありますので、お気軽にご参加くださいませ。