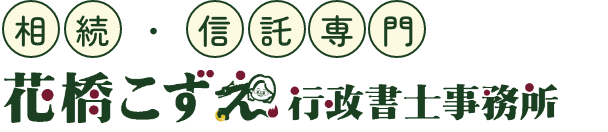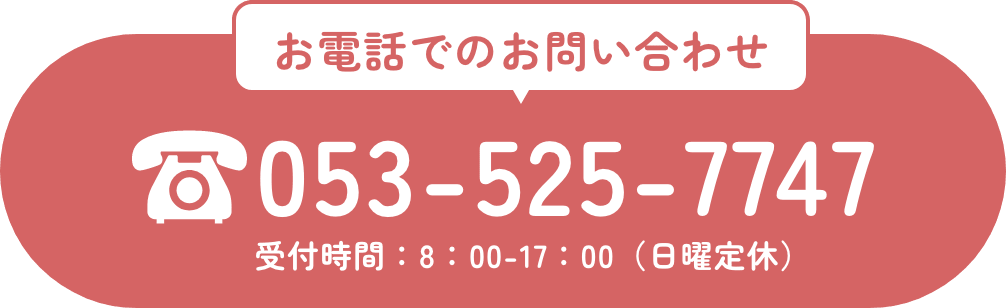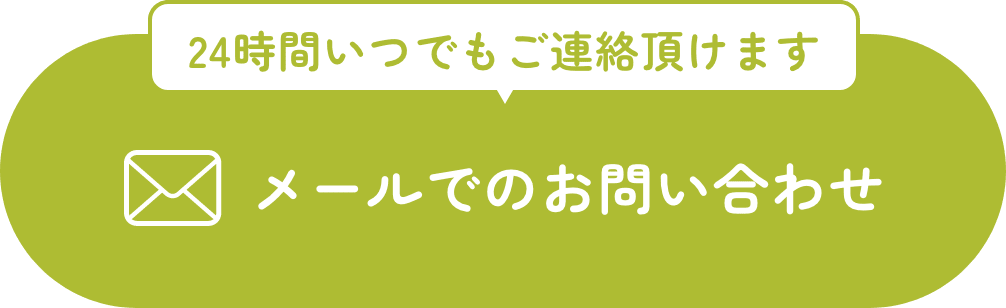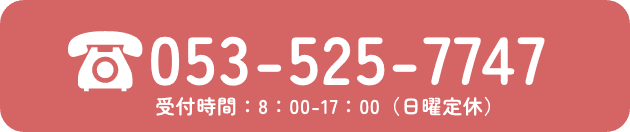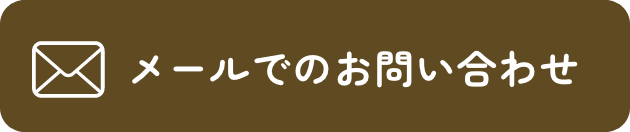ペット信託ってなに??

ペット信託って聞いたことありますか?
実は、アメリカでは昔からペット信託が活用されてきたんです。アメリカでは財産法人という法人を作れますから、ペットのために法人を作るんですね。そして、その法人に財産を渡せば、法人の管理者がペットを飼育するという制度なのです。日本の場合とはぜんぜん違いますね。
日本の場合は、財産を持てるのは、個人または法人ですから、なかなかアメリカのように「ペットのためだけに」財産を持たせるということができないんですね。
そこで、今日は信託法を活用した「ペット信託」ってどういうものなのか?ということをお話してみたいと思います。
自分亡き後、ペットの老後をどうするか?
今の時代、ペットは家族の一員です。飼い主である自分も高齢になってきて、次の飼い主も決まっておらず、認知症や死亡でペットが飼えなくなってしまうことが心配だという方は増えてきています。
一般的な対策しても限界があります。
・財産を誰かに預けたとしても、単に預けただけでは、自分が死んだ後に相続財産になってしまう。
・財産が相続されてしまうと、その相続財産をどう使うかは、相続人次第になってしまう。
・負担付遺贈をしても、受遺者が必ず約束を守ってくれるとは限らない。
そこでペット信託を活用したらどうなる?!
ペット信託を行うために大切なことは、飼い主の死亡時に緊急対応ができること、そして、飼育施設の確保が何より大事になります。
そのため、ペット信託は法律面だけでなく、施設の確保、飼育費の計算、ペット自体の動物としての特性を知って、オーダーメイドで信託の全体を組み立てる必要があります。
例えば、寿命の長い動物(鳥や亀など)は、寿命までにいったいいくらかかるのか?というペット自体の特性を考えて金額を決めなければいけません。
ペット自体を信託の対象とします。
ペットは民法上では「動産」です。このことに注目して、ペット自体を動産信託として信託財産にします。合わせて金銭も信託し、その金銭で世話代などに充てる仕組みです。
受託者は信託財産を管理・運用・処分する権限(義務)がありますから、信託財産であるペットを飼育する義務は受託者に生じます。受託者はそのために信託財産を支出することができます。
ここでご注意いただきたいのは、受託者は決して自分でペットのお世話をしなければならないわけではないんです。実務的なペットのお世話はそのような施設にお願いすることができます。
もちろん、自分で飼育することもできますが、自分で飼えなければ施設にお願いすれば良いんです。
ペット信託しなかったら?
飼い主が亡くなったら、相続になります。当然ペットも相続財産になりますから、相続人に引き渡されますが、相続人がペットが嫌いだったらどうなるでしょう。
最悪は殺処分まで考えなければならない状況になってしまうのではないでしょうか。
相続人がペットの飼育を拒否して「殺処分する」と言ったときには誰もそれに逆らうことはできないんです。
信託であれば
ペット信託を活用すれば、ペットと共に信託された財産は、ペットのために使うことができるようになります。
里親としてペットを引き受けてくれる人が現れれば、信託財産から御礼をお渡しすることももちろん可能なんです。
ペット信託の受益権は
制限付き受益権になります。
受益者は、制限が解除されるまで自由に権利を行使できないわけです。そしてその制限というのは、ペットが天寿をまっとうするまで。としておくことです。
このようにすれば、ペットが天寿をまっとうするまで、受益者としての権利は使えなくなりますので、安心ですね。
ペットが天寿をまっとうした後にお金が残っていれば、それは二次受益者に渡されることになります。
必要に応じて「信託監督人」を置くことで必要なときにアドバイスをもらうことができます。
ここでいう信託監督人は、ペットに詳しい人がベストですね。
信託の終了についても制限がかかっています。
上記の例でいきますと、ペットが天寿をまっとうするまでは信託は終了することはできません。
そのため、ペットの施設で飼育を続けるのも良いですが、里親制度で里親に渡すことになれば信託を終了する要件を満たすことができるので、この時点で信託を終了します。
このように信託契約書の中身が大事なんです。上記の内容をすべて網羅したものにしなければなりません。
いかがでしたか?
大切な家族であるペットの今後を心配される方はとても多いですので、ペット信託についてご興味がある方はぜひ、お気軽にご連絡いただければ幸いです。
花橋こずえ行政書士事務所では初回60分の無料相談を設けておりますので、ぜひ有効にご活用をお願いいたします。